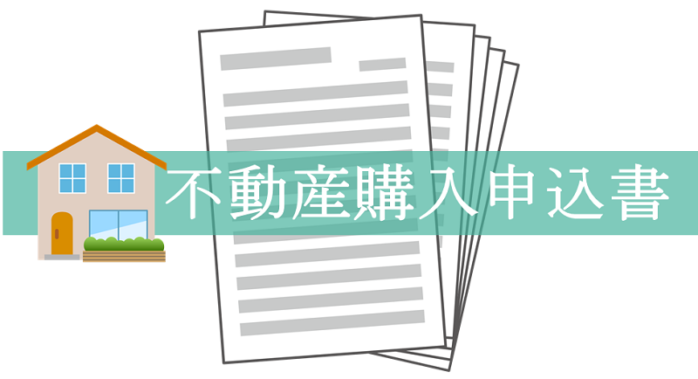内見者があなたの家を買いたいという意思が固まったら、売主であるあなたに対して「不動産購入申込書」が提出されます。
この記事では、不動産購入申込書の効力や確認すべき7つのポイントについてお伝えします。
不動産購入申込書とは
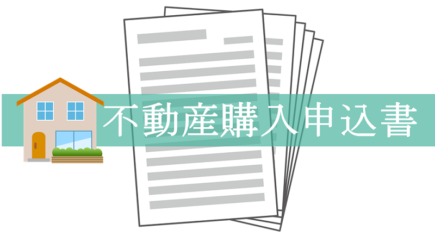
不動産購入申込書とは、買主から売主に向けて購入希望価格や条件などが記載された書類で、契約「前」の交渉で使用します。
このタイミングが売主から条件を提示できる唯一の機会だと思って臨む必要があります。
なお不動産購入申込書に統一された書式はなく、不動産屋によって色々です。
また呼び名も「買付申込書」や「買付証明書」など不動産屋によって異なる場合があります。
不動産購入申込書の効力は?キャンセルは?
不動産購入申込書は契約書ではなく、あくまでも買主から売主へ「購入の意思」を伝えるものなので、申し込みをしたからといって契約が成立するわけではありません。
条件等によっては、売主が拒否することは可能です。
また不動産購入申込書が提出され、売主が承諾した後でも、買主は「やっぱりやめます」とキャンセルすることができます。
売買契約であればキャンセル(=解約)すると手付金が返金されなかったり、違約金が生じたりしますが、
不動産購入申込書はキャンセルしても原則として費用がかかることはありません。
このキャンセルのしさは「不動産購入申込書」と「不動産売買契約書」の大きな違いと言えます。
不動産購入申込書7つの確認ポイント
不動産購入申込書で確認していくべきポイントは7つあります。
1:価格交渉
もしも買主が値下げを希望している場合は、不動産購入申込書をもらってから価格交渉を始めます。
不動産購入申込書をもらう前に「いくらぐらいまでなら値下げできますか?」と買主側の不動産屋が雑談のように聞いてくることがあります。
ですが、あくまでも不動産購入申込書が届いた時が正式な交渉の開始なので、その前に明言をする必要はありません。
買主が不動産購入申込書に記載した価格を受け入れる時は、慎重に判断します。
一度その価格を受け入れてしまったら、売主・買主双方の不動産屋も「その価格までなら値下げしてもいいんだな」と判断するからです。
そして、もしその不動産購入申込書が撤回された後から別の購入希望者が現れた時に「○○円までなら値下げできそうですよ」と伝わってしまう可能性があるからです。
価格交渉の中には、切りよく数十万円をカットするだけのものもあれば、数百万円単位の値下げ希望まであります。
ここで回答した価格が最終的な売却価格となるので、買主の本気度を見極めつつ、慎重に決めてください。
2:手付金

手付金とは、不動産売買契約の際に買主が売主に渡すお金で、売買代金の一部に充当されるものです。
残金は売却物件の引き渡しの段階で支払われることが一般的です。
手付金の額は、売買代金に合わせて50万円や100万円など切りのいい数字を収めてもらうことが多いです。
なお売買契約が済んだ後でも
- 買主は手付金を放棄
- 売主は手付金を返却して、さらに同額を上乗せして買主に支払う(=手付倍返し)
というペナルティーで売買契約を破棄することができます。
したがって手付金の額が少ないほど、手付金を放棄するだけで売買契約をすぐに破棄できてしまうので、売主にとっても買主にとっても契約は不安定な状態といえます。
すぐに破棄される売買契約にしないためにも、万が一不動産購入申込書に書かれた手付金の額が少ない場合には、一定額を入れてもらうよう営業担当者に相談しましょう。
3:引き渡し日
引き渡し日は双方の事情を考慮した話し合いで決められるものですが、一般的には売買契約後1~3カ月以内が引き渡し日とされます。
買主側のよくある要望
年末から春にかけての交渉でよくあるのが、買主側から「新学期に合わせて、3月に引き渡して欲しい」という要望です。
売主としては可能な限り要望に応えてあげれば良いのですが、あまりにも売買契約から引き渡しまでの期間が長すぎる場合には注意が必要です。
その間に買主の気持ちが変わり、決済が行われない可能性も0とは言い切れません。
引き渡しまでの期間が長い場合には、手付金を少し多めに要求するのも一つの方法です。
売主側のよくある要望
一方、住み替えする売主側の要望として多いのが、家の引き渡し当日に売買残金の授受が行われるのが一般的な中、「引き渡し日を決済日以降にして欲しい」というものです。
家や土地を売ったお金を住み替え先の購入に当てる場合、売買代金の授受を行ってからの引っ越しになるからです。
これを「引き渡し猶予」といい、その交渉も不動産購入申込書に回答する際に行います。
引き渡し猶予として提示できる期間は、通常1週間です。
この1週間のうちは売却した家に無料で住まわせてもらうことが可能です。
4:住宅ローン特約
個人が現金一括で家を購入することは稀であり、住宅ローンを借りて購入するケースがほとんどです。
そして買主が住宅ローンを利用する場合、ほぼ必ず「住宅ローン特約あり」での申し込みになります。
住宅ローン特約とは
住宅ローン特約とは、売買契約後に万が一住宅ローンの審査が通らなかった場合には、契約を白紙撤回するというものです。
通常、売買契約後に約3週間の期間を設け、買主はその間に住宅ローンの審査を受けます。
そして審査が通ったら晴れて決済(引き渡し)となります。
住宅ローン特約を承諾する際の注意点1
住宅ローン特約は一般的な条項なので売主は承諾するのが普通ですが、リスクもあります。
それは買主が住宅ローンの審査を受けている間、販売活動をストップせざるを得ないという点です。
もし審査に通らなかったら、3週間が丸々ムダになってしまい、また一からやり直しという時間的ロスが発生します。
ただし少し工夫すれば、融資審査結果を待つまでの時間をムダにせずに済みます。
それは不動産購入申込書に書かれた買主の収入や資金計画の状況から、審査に通りにくいかどうかを推測することです。
勤め先が小規模企業や自営業の場合は審査に通りづらいと考えられるので、金融機関に事前申込してもらうよう伝えましょう。
金融機関は正式審査の前に事前審査をしてくれます。
事前審査でローンが下りるとわかってから売買契約を結んでもらえば、住宅ローン特約で白紙撤回されるのを防ぐことができます。
ただし買主の資金状況を勘ぐることになるので、失礼のないよう慎重に対応してもらえるよう営業担当者にお願いしましょう。
住宅ローン特約を承諾する際の注意点2
もう1つ注意したいのが、住宅ローン特約が「解除保留型」になっていないかどうかです。
住宅ローン特約には「解除条件型」と「解除保留型」があります。
- 解除条件型:設定した期間内に融資審査が通らなければ、自動的に契約が解除になるもの
- 解除保留型:設定した期間内に融資審査が通らなければ、その旨を売主に通知して、契約を白紙にするもの
つまり解除保留型の場合、買主が契約を白紙にすると意思表示しない限り、期間が過ぎたら契約が成立することになります。
この「解除保留型」は最もトラブルが多いものです。
なぜなら買主が融資審査に通らなかったことを売主に伝え忘れたり、間に入っている不動産屋の営業担当者が連絡手続きを忘れたりするからです。
売主としては、買主が融資審査に通らないなら、速やかに次の買主を探したいですよね。
住宅ローン特約の条件が「解除保留型」なのは珍しいケースではありますが、念のため確認しておきましょう。
5:瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、建物に買主が知り得なかった瑕疵(欠陥)が発生した場合、売主の責任で修理するという取り決めです。
この保証の有無や期間も、交渉で決まります。
引き渡し後3カ月以内とすることが多いようですが、そもそも瑕疵担保責任をつけないケースもあります。
ちなみに我が家が住み替え先の家(京都)を購入した際は、わずか1週間だけとなりました。
どのような瑕疵であれば担保責任が生じるのかは「物件状況報告書」の中身によって変わります。
なお既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、万が一瑕疵が見つかった場合でも補修費を保険で対応できるので、売主にとっても買主にとっても安心できます。
6:測量の実施と境界明示

一戸建てに限ったことですが、売買契約にあたって測量の実施や境界の明示が要求されます。
土地には必ず隣地との境界がありますが、曖昧になっていると後々買主がその物件を売却したりリフォームしたりする際にトラブルになる恐れがあるので、所有権を移転する際に明確にする必要があるのです。
なお測量図が手元にない場合、測量をしてもらう必要がありますが、測量の時期が売買契約後になってしまうこともあります。
そうすると登記簿に書かれている「公簿面積」と、測量した時の「実測面積」に差が生じることがあるので、その場合の対応についても契約書に記載しておく必要があります。
- 公簿売買:公簿面積と実測面積の差を精算せずに売買する
- 実測売買:契約後に公簿面積と実測面積の差を計算し、面積の増減分を価格に反映させて精算する
境界明示の際には隣接地の所有者に立ち会ってもらいます。
隣接地の所有者の承諾が得られなければ、境界を確定することができません。
隣接地の所有者がそこに住んでいれば手間はないのですが、遠方に住んでいる場合は境界明示までに時間がかかります。
したがって境界の明示は、売却を依頼した段階で不動産屋に相談しておいた方が良いです。
測量や境界明示は不動産屋を通して測量士や土地家屋調査士に依頼するのが普通で、費用は20万円~100万円が目安です。
物件の状況によって幅があるため、費用の目安は事前に不動産屋に確認しておくと安心です。
7:更地渡し
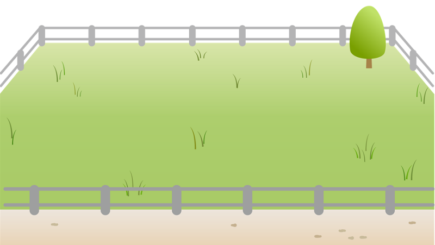
更地渡しも一戸建てに限ったことですが、売主の費用負担で家を壊してから引き渡しすることを条件としてくる場合も稀にあります。
更地渡しでも売却できれば良いのですが、実際に更地にした後に、何らかの事情で決済(引き渡し)がされなければ、更地にしたことがムダになってしまいます。
そのため更地渡しの条件を認める場合でも、実際に更地にするのは住宅ローンの審査が通った後にするなど、タイミングに注意が必要です。
以上、不動産購入申込書の効力と確認すべき7点をお伝えしました。
疑問点や交渉したい点があったら、買主ではなく、まずは営業担当者に相談してください。